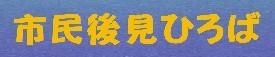第1回オンライン勉強会(2025年6月21日)
2025年6月21日、「第1回オンライン勉強会」が開催され、認定NPO法人市民後見センターさいたま 顧問・中田均氏を講師に迎え、「何をめざしてNPOを立ち上げ、成年後見の受任活動を行っているのか」をテーマに講演が行われました。当日は、スタッフを含め約40名が参加しました。
本講演では、NPO法人の設立経緯から、運営方針や維持の工夫について紹介されました。以下、概要を報告します。
市民後見人養成講座を修了後、市民感覚を大切にし、障害者を中心とした権利擁護活動を推進すべくNPO法人を設立。
運営の維持にあたっては、助成金に依存することなく、継続的に安定した資金を確保することが重要であるとし、資金調達の工夫についても説明がありました。認定NPO法人は、寄付や遺贈に税制優遇があるため資金面では有利な一方、100名以上の寄付者の確保や厳格な監査への対応が求められることに言及されました。
また、運用面では、不正防止の観点から1案件につき3名体制とし、成年後見賠償責任保険などに加入しているとのことです。
受任対象者は「親族が身近にいない、中程度の資産を有する方」を中心とし、任意後見を軸に、見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約などを組み合わせた総合的な支援を提供していることが紹介されました。活動には、社会福祉士・ケアマネジャー・臨床心理士など、多様な専門職がスタッフとして参加しており、地域の中核機関にも参画しているとのことです。
包括支援センター、福祉施設、社協などとの連携により受任件数を増やすことは可能ですが、それに伴い、スタッフの増員が課題であるとの認識が示されました。
今後は、受任件数50〜100件を目標に、高齢者の終身サポート事業や後見監督人の受任など、活動の幅をさらに広げていく方針が示されました。地域の関係機関や住民と協力し、誰もが安心して暮らせる仕組み、すなわち「地域共助」の実現に向けた取り組みを続けていくとの展望が示されました。
17期修了生交流会開催(2025年4月13日)
4月13日13時より、第17期市民後見人養成講座を修了された皆さまの交流会をオンラインで開催いたしました。
当日は、17期修了生15名と市民後見ひろばスタッフ7名が参加しました。
まず、市民後見ひろばの活動をご紹介した後、3つのグループに分かれて、養成講座を受講した動機や今後の活動などについて、自己紹介を交えながら交流を行いました。続いて全体ミーティングが行われ、「任意後見制度の現状と課題」「報酬額のあり方」「法人後見の対応」「転居が困難な方への支援」など、実際の現場で直面するテーマについて、意見交換が行われました。
オンライン勉強会「最近話題の意思決定支援とは?」(2025年3月23日)
3月23日にオンライン勉強会を開催しました。
まず、厚生労働省作成の動画「意思決定支援の基本的な考え方」を視聴した後、グループに分かれて意見交換を行いました。
今回の勉強会には、現場で意思決定支援に携わる方、ご家族の意思決定に直面された方、意思決定支援を学びたい方など、さまざまな立場の28名が参加しました。
議論を通じて、精神疾患のあるご家族を支える際の困難や、介護専門職の支援の重要性、地域ぐるみで支えることの意義について理解を深めることができました。また、ガイドラインに基づいた意思決定支援がパターン化・マニュアル化される一方で、個別支援の必要性を改めて実感したとの意見も寄せられ、大変有意義な学びの機会となりました。
オンラインセミナー 「知っておきたい介護保険制度~介護とお金の話~」(2024年12月21日)
2024年12月21日(土)13時より、「知っておきたい介護保険制度~介護とお金の話~」と題し、Zoomを使用したオンライン講習会を開催いたしました。
講師には、黒田尚子氏(黒田FPオフィス代表・一般社団法人患者家計サポート協会顧問)をお迎えし、全国から47名の参加がありました。
講義では、介護保険の基礎知識を学び、介護にかかる費用について具体的な数字を交えながら現状を共有することができました。また、親が介護保険を利用する前にできる準備として、地域の社会資源の確認や相談窓口の活用、介護にかかる費用の把握が重要であることが強調されておりました。さらに、限られたお金を効果的に活用するため、自分に必要な情報を事前に収集することの大切さについても言及がありました。
休憩後の質疑応答では、次のような実践的な質問が寄せられました。
「老々介護状態だが、子としてどの程度関わるのが良いか。また、老健施設を利用した場合の費用はどのくらいか。」
「両親が介護状態にあり、母が倒れてリハビリ中のため、相談先を教えてほしい」
いずれも、親の介護に直面する参加者の切実な質問でした。
2時間にわたる講習会は、特に親の介護を控える世代にとって色々と考えさせられる機会となり、大変有意義なものとなりました。
オンライン勉強会「成年後見受任体験談」(2024年9月21日)
9月21日(土)13時より、東京都消費生活総合センターの会議室で開催しました。オンラインを併用したハイブリット形式で行われ、23名が参加しました。
講師に市民後見人養成講座7期生の宗村憲氏をお迎えし、「成年後見の受任をしたきっかけと活動を続ける上での体験したこと」をテーマにお話しいただきました。
宗村氏は社会福祉士として「ぱあとな」に所属し受任活動を開始しましたが、所属していた社会福祉事務所の代表が体調を崩されたことをきっかけに、法人を立ち上げ現在に至っております。法人後見に移行できたことで、自分だけで背負わなければならないという心理負担がなくなり業務も分担できたことで、心労の負荷は軽減されたとのことです。
受任に向けては、本人や本人の支援者からの信頼が重要で、受任実績があると事前に打診されることが多くなるとのことです。
これから受任活動を考えている方には、まずは「日常生活自立支援事業」など自治体の活動に参加して経験を積むことや、研修などを受講し人脈を広げることが大切だとお話しされました。
講演後はグループに分かれて講演の感想などが話し合われ、その後全体交流が行われ勉強会は終了となりました。
市民後見人養成講座修了生(16期)オンライン交流会(2024年4月21日)
4月21日(日曜日)オンラインによる第16期修了生向けの交流会を開催しました。21名の修了生が参加し、2時間交流を深めました。
今回の市民後見人養成講座も昨年度同様に対面講義とオンライン講義のふたつの受講コースがあり、修了生同士が意見交換をする時間を持てなかったとの意見がありました。まず3グループに分かれて、自己紹介と養成講座を修了してこれからどのような活動をしていきたいかなどの話をしました。グループワークを終えて、参加者全員で話し合う機会を設けました。
高齢者の居場所づくりをしている方や社会福祉協議会に勤めている方、実際にNPO法人で成年後見を受任されている方、地方でケアマネジャーをしている方など様々な職種の人たちが集まったおかげで勉強になる情報をお互いに提供しあうことができました。とくに市民後見人として活動するにはどうしたらいいのかなどの質問が多くありました。地元の社会福祉協議会に行き問い合わせをした方も何人かおり、それぞれの地域の社協で異なる対応をしていました。まずはこちらから積極的に社協へ問い合わせることが大事だと思いました。
交流会終了後アンケートをとったところ、「様々な経験をお持ちの皆さんのお話を伺うことができたので良かった」などの感想がありました。また「修了生が立ち上げた組織(団体、NPO法人)の紹介やどうやって立ち上げたのかを聞きたい」との要望がありました。これらの意見を活かして、今後の市民後見ひろばでは活動していきます。
オンラインセミナー 終活・もしもの事があった時(2024年3月2日)
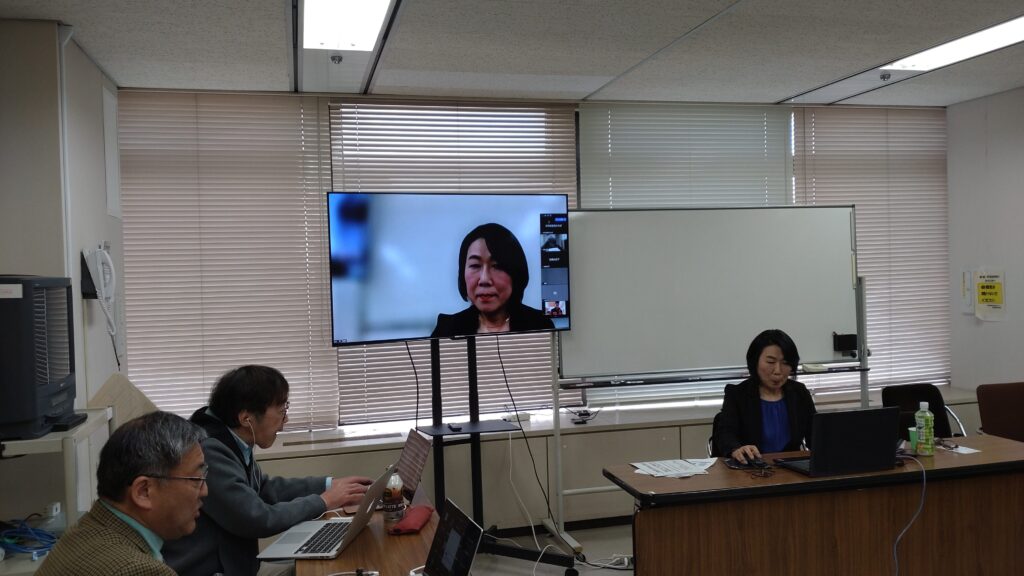
3月2日㈯13時より学習会を開催しました。今回は初めて、会場とオンラインを併用したハイブリット方式で開催し、47名の会員が参加しました。
学習会は、「終活・もしもの事があった時~市民後見人として知っておくべきこと」のテーマで、(一社)包括あんしん協会代表理事 大和泰子氏に講義いただきました。
講義の概要を紹介します。
2025年には65歳以上の単身者は725万人と予想され、5人に2人はおひとり世帯となる見込みであること、東京都23区の孤独死は6,000人超(令和2年)などのデータを示し、一人暮らしの孤独死問題が指摘されました。
『一人暮らしの高齢者が備えるべきポイントとしては、「緊急連絡先」「身元引受人」「入院時や介護申請時の手続き人」など支援者・支援事業者を事前に決めておくことが大切です。身元保証契約や任意後見契約、死後事務委任契約などの制度を活用することで、万が一の時にスムーズなサポートが可能となります。』と、大和氏からは、事例を交えながら具体的なアドバイスが提供されました。
学習会では質疑応答の時間が設けられ、参加者からは「保証人が医療同意を求められた場合の対処法は?」「保証人が連帯保証した際の資金不足への対応策は?」「任意後見契約において監督人の指示が本人の意向に添わない場合はどうしたらよいか?」など、高度な質問が寄せられました。学習会終了後に行われた交流会では、「具体例を交えた講義が理解しやすかった」「身元保証人に関する情報が参考になった」といった学習会への好評の声が寄せられました。また、参加者同士の交流や近況報告も行われ、有意義なひとときとなりました。
オンライン勉強会 事例で考える市民後見人Vol.2(2023年6月18日)
6月18日に第3回オンライン交流会が開催されました。
今回は、知的障害者を支援する後見活動を事例として取り上げております。
参加者34名が5グループに分けれて意見交流をし、その後、全体交流において、各グループで話し合われたことが発表されました。
〇今回の事例(社会福祉士による後見取組)はこちらから
〇事例についての主な意見
・グループホーム入所後のアセスメントができていない。ケアマネジメントや支援者の連携で利用者をサポートする力の大切さを感じた。
・50歳の知的障害者ですと、息の長い付き合いが必要となる。どうやって繋いでいくか、チーム活動が鍵となる。
・グループホームまでの調整期間が短く、本人の意思がどこまで反映されているか、疑問に思う。
・本人と支援者との相性が重要である。
・本人が50歳に至るまで、支援ができていないことが課題である。
・ジョブコーチ、生活支援者、後見人それぞれが、連携して対応することが重要である。
〇事例以外の意見は次の通りです。
・障害者は在宅していると、65歳から介護保険となり、今まで利用できたものができなくなる。いわゆる65歳の壁が問題である。
・福祉支援のすき間を補う活動として、社協が中心となり立ち上げられた「有償ボランティア」がある。
・市民後見人と専門職後見人の活動に温度差がある。専門職は自分の立場を守る活動となっている。市民後見人は知識が少ないが、専門職後見人がやらない活動もしている。
・後見人の活動が見えないと知的障害をもつ子の親は心配。
最後に、「後見人は本人とどう向き合うかが大切。アセスメントをどう組み立てるのかを考えなければならない。相性も大事だが、人間関係をどう作るかを意識して、本人とチームが一緒になって関係作りを構築することが大切である。」と総括して閉会しました。
市民後見人養成講座修了生(15期)オンライン交流会(2023年4月9日)
15期修了生を対象としたオンライン交流会が開催され、15期修了生16名 スタッフ6名 計22名が参加しました。
すでに法人で後見活動をされている方、後見活動を一歩踏み出した方、福祉の最前線で働いている方、働きながら後見活動に携わっていきたい方、これから活動を始めたいと思っている方など様々な方々が参加されました。
交流会は、市民後見ひろばの活動を紹介した後、4つのグループに分かれ修了生の交流が始まりました。自己紹介に続いて、養成講座を受講した動機や今後活動したいことなど、それぞれのグループで意見交換が行われました。
その後、全体交流が行われ、各グループから意見交換の内容が発表されました。発表された内容の一部を紹介します。
受講した動機については、「障害者の相談支援員として活動しながら後見人が不足しているいることを実感した」「親族の後見利用がきっかけとなった」「身近の高齢者に接して後見の必要性を感じた」「後見につなげる仕事をしながら、後見が利用できないもどかしさを感じた」など様々なお話がありました。
今後の活動については「活動をしたいがどのように関わればよいか知りたい」「地域に適当な法人がないので情報が欲しい」など、積極的な意見が多かったです。後見活動をされている方からは「後見の需要が増えている反面、後見活動を希望している人が結びつけられない。」など、マッチングの課題が指摘されました。
「まだまだ後見制度が知れ渡っていない。広報活動も我々の使命ではないか。」を結びの言葉とし終了いたしました。
オンラインセミナー 消費者センターの役割と最近の高齢者被害(2022年9月25日)
全国消費生活相談員協会会員 廣重美希氏をお招きし、「消費者センターの役割と最近の高齢者被害」と題したオンライン講演会を開催しました。
廣重氏は 消費生活センターでの相談員を23年勤務し、現在市民後見人でもあります。
講演の概要を紹介します。
消費生活センターは「消費者と事業者との契約」や「製品事故」についての相談を扱っており、相談件数は2004年をピークに減少し、ここ何年かは横ばい状況です。ただ、近年は、サイトの詐欺により、契約解除に至るまで、決済代行会社など多数の会社と交渉することになり複雑化しております。
高齢者の被害は、家族からの相談が多く、被害者が認知症の場合は、本人が契約解除しなければならず、解決が難しいことが多いです。高齢者に見られる被害の購入形態は、訪問販売、電話勧誘販売が6割を占めております。
いくつかの高齢者トラブルとして悪質業者の手口を紹介し、困ったときは消費生活センターへ相談することを促しておりました。
未然に防ぐ手段として、「訪問販売お断りステッカー」や「留守電対応」をあげております。
また、迷惑なダイレクトメールは、「受取を拒絶します」と明記し署名・押印したメモを郵便物に添付して返送することや、訪問販売の解除は、クーリングオフ制度を活用して、ハガキ等で販売業者、該当商品名等を記載し、販売店宛て「特定記録郵便」で通達する、などの対処方法が紹介されました。
高齢者の見守り活動としては、高齢者が持つ「お金」「健康」「孤独」をキーに、「見慣れない段ボールが山積み」とか「見慣れない人や車が出入りしている」などの見守りチェックポイントを設けケアしてほしいと結んでおります。
参加者からは、新たに知りえたことが多く、ためになったとの声をいただきました。
オンライン勉強会 事例で考える市民後見Vol.1(2022年5月29日)
5月29日に「市民後見ひろばオンライン交流 事例で考える市民後見」が開催されました。参加者は29名でした。参加者には事前に事例の内容を目通しいただき、当日は6つのグループに分かれ、事例について意見交換をしながら交流をしていただきました。その後、各グループで話し合われた内容が発表され、全員で共有いたしました。
【事例の要旨】
Aさん(80歳)は独り暮らしで、家はゴミ屋敷状態。住民からの連絡により地域包括支援センターが支援に入る。Aさんは、要介護2の認定を受け、ケアマネによる在宅介護支援の実施で、通常の生活ができる状況になった。
その後、Aさんは転倒により入院したが、唯一の親族である息子さんからは支援を拒絶されている。脳梗塞が原因で片麻痺となり、車いす生活となった。この時点で「要介護3」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲ」の状況。ケアマネさんは、施設への入所と後見制度の利用を考えている。
【話し合われた内容】
・ゴミ屋敷になる前の段階での支援が望ましいが、地域との接点がないと把握が難しい。見守り活動などで地域につなぐことが大切。
・意思決定支援により本人の意思確認が優先される。だが、知的障害者の意思確認は困難。
・現場の声として、後見は早い時期から利用してほしい。
・医療行為の同意などは後見人ではできないので、親族の関かわりが必要になる。親族とのコミュニケーションが優先される。