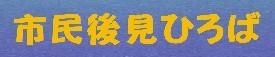■第19回ひろばの輪<オンライン>(2025年3月23日)
”今話題の意思決定支援とは?”
3月23日にオンライン勉強会を開催しました。
まず、厚生労働省作成の動画「意思決定支援の基本的な考え方」を視聴した後、グループに分かれて意見交換を行いました。
今回の勉強会には、現場で意思決定支援に携わる方、ご家族の意思決定に直面された方、意思決定支援を学びたい方など、さまざまな立場の28名が参加しました。
議論を通じて、精神疾患のあるご家族を支える際の困難や、介護専門職の支援の重要性、地域ぐるみで支えることの意義について理解を深めることができました。また、ガイドラインに基づいた意思決定支援がパターン化・マニュアル化される一方で、個別支援の必要性を改めて実感したとの意見も寄せられ、大変有意義な学びの機会となりました。
■第18回ひろばの輪<オンライン>(2024年9月21日)
”後見受任体験談を聞こう”
9月21日(土)13時より、東京都消費生活総合センターの会議室にて開催し、オンラインを併用したハイブリット形式で行われ、23名が参加しました。
講師に市民後見人養成講座7期生の宗村憲氏をお迎えし、「成年後見の受任をしたきっかけと活動を続ける上での体験したこと」をテーマにお話しいただきました。
宗村氏は社会福祉士として「ぱあとな」に所属し受任活動を開始しましたが、所属していた社会福祉事務所の代表が体調を崩されたことをきっかけに、法人を立ち上げ現在に至っております。法人後見に移行できたことで、自分だけで背負わなければならないという心理負担がなくなり業務も分担できたことで、心労の負荷は軽減されたとのことです。
受任に向けては、本人や本人の支援者からの信頼が重要で、受任実績があると事前に打診されることが多くなるとのことです。
これから受任活動を考えている方には、まずは「日常生活自立支援事業」など自治体の活動に参加して経験を積むことや、研修などを受講し人脈を広げることが大切だとお話しされました。
講演後はグループに分かれて講演の感想などが話し合われ、その後全体交流が行われ勉強会は終了となりました。
■第17回ひろばの輪<オンライン>(2023年6月18日)
”事例で考える市民後見Vol.2”
6月18日に第3回オンライン交流会が開催されました。
今回は、知的障害者を支援する後見活動を事例として取り上げております。
参加者34名が5グループに分けれて意見交流をし、その後、全体交流において、各グループで話し合われたことが発表されました。
〇今回の事例(社会福祉士による後見取組)はこちらから
〇事例についての主な意見
・グループホーム入所後のアセスメントができていない。ケアマネジメントや支援者の連携で利用者をサポートする力の大切さを感じた。
・50歳の知的障害者ですと、息の長い付き合いが必要となる。どうやって繋いでいくか、チーム活動が鍵となる。
・グループホームまでの調整期間が短く、本人の意思がどこまで反映されているか、疑問に思う。
・本人と支援者との相性が重要である。
・本人が50歳に至るまで、支援ができていないことが課題である。
・ジョブコーチ、生活支援者、後見人それぞれが、連携して対応することが重要である。
〇事例以外の意見は次の通りです。
・障害者は在宅していると、65歳から介護保険となり、今まで利用できたものができなくなる。いわゆる65歳の壁が問題である。
・福祉支援のすき間を補う活動として、社協が中心となり立ち上げられた「有償ボランティア」がある。
・市民後見人と専門職後見人の活動に温度差がある。専門職は自分の立場を守る活動となっている。市民後見人は知識が少ないが、専門職後見人がやらない活動もしている。
・後見人の活動が見えないと知的障害をもつ子の親は心配。
最後に、「後見人は本人とどう向き合うかが大切。アセスメントをどう組み立てるのかを考えなければならない。相性も大事だが、人間関係をどう作るかを意識して、本人とチームが一緒になって関係作りを構築することが大切である。」と総括して閉会しました。
■第16回ひろばの輪<オンライン>(2022年5月29日)
”事例で考える市民後見Vol.1”
5月29日に「市民後見ひろばオンライン交流 事例で考える市民後見」が開催されました。参加者は29名でした。参加者には事前に事例の内容を目通しいただき、当日は6つのグループに分かれ、事例について意見交換をしながら交流をしていただきました。その後、各グループで話し合われた内容が発表され、全員で共有いたしました。
【事例の要旨】
Aさん(80歳)は独り暮らしで、家はゴミ屋敷状態。住民からの連絡により地域包括支援センターが支援に入る。Aさんは、要介護2の認定を受け、ケアマネによる在宅介護支援の実施で、通常の生活ができる状況になった。
その後、Aさんは転倒により入院したが、唯一の親族である息子さんからは支援を拒絶されている。脳梗塞が原因で片麻痺となり、車いす生活となった。この時点で「要介護3」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲ」の状況。ケアマネさんは、施設への入所と後見制度の利用を考えている。
【話し合われた内容】
・ゴミ屋敷になる前の段階での支援が望ましいが、地域との接点がないと把握が難しい。見守り活動などで地域につなぐことが大切。
・意思決定支援により本人の意思確認が優先される。だが、知的障害者の意思確認は困難。
・現場の声として、後見は早い時期から利用してほしい。
・医療行為の同意などは後見人ではできないので、親族の関かわりが必要になる。親族とのコミュニケーションが優先される。
■第15回ひろばの輪 (2019年9月22日)
“丸投げしない老後の暮らし方第2弾~どんな状態になっても最後までその人らしい暮らしをデザインする~”
全国マイケアプラン・ネットワーク 代表 島村八重子氏と須田正子氏に再び登壇いただき、成年後見人は、被後見人が最後までその人らしく暮らせるようにデザインするのが仕事とし、どのようにすれば、その人らしく暮らしていくか、どのようなことが本人や家族のそれぞれの意向にそえるのかを、ロールプレイを通して参加者みんなでで考えるワークショップを行いました。(於:飯田橋ボランティアセンター)
■第14回ひろばの輪 (2018年12月8日)
“聞いてみよう、成年後見NPO法人の立ち上げとこれからの活動”
今回は市民後見ひろばの会員(6期生)であり、本年5月に国分寺市にて「NPO法人成年後見ウィル」を設立した寺内芳樹氏を講師としてお招きし、NPO法人設立までの経緯や苦労話、これからどのような活動をして行くかなどのお話をしていただきました。また、成年後見ウィルの特徴である障がい者家族との関わりや社会福祉協議会などと地域ネットワークをどのように構築するかなどについてのお話もありました。(於:東京芸術劇場 6Fミーティングルーム)
■第13回ひろばの輪 (2018年9月8日)
“失語症を通して、被後見人とのコミュニケーションを学ぶ”
NPO法人日本失語症協議会の方を招き、失語症を学び、本人の意思をくみ取るコミュニケーションの工夫について学びました。お招きした講師は、NPO法人失語症協議会事務局長兼㈱言語生活サポートセンター代表園田尚美氏、坂井道子氏です。失語症の方の症状は一人ひとり異なり、千差万別です。どのような支援があれば、失語症のある方々の基本的人権を守れるのか、失語症のある方が当たり前の生活を送ることが可能なのかの講義を拝聴しました。(於:東京芸術劇場 6Fミーティングルーム)
■第12回ひろばの輪 (2018年6月10日)
“高齢者に対する悪質商法の実態と被害防止方法を学ぶ”
京都消費者生活総合センターより講師をお招きし、悪質商法の現状や対策について講義を拝聴しました。後半は、『高額な着物を何枚も購入してしまう被補助人』と題して、参加者が本人、補助人、ヘルパーさん、消費者センター相談人を演じるロールプレイングを行い、悪徳商法に対して実際どのように解決するかを具体的に学びました。(於:千代田区万世橋区民会館)
■第11回ひろばの輪 (2018年4月15日)
“丸投げしない老後の暮らし方 ~あなたが要介護になったとしたらどうしたいですか?~”
全国マイケアプラン・ネットワーク 島村八重子氏、須田正子氏をお招きし、「某国民的アニメの30年後」をイメージした疑似家族になり、「82歳女性が要介護認定1となった。明日からの暮らしを考えよう」という題でワークショップを行いました。(於:マイルドハート高円寺)
■第10回ひろばの輪 (2018年1月14日)
“改めて学ぼう。認知症の方への接し方”

秋元弘子先生をお招きし「認知症」について学びました。前半は「認知症の基礎学習」として、「認知症の人の行動や態度は、その人の性格や素質、周囲との人間関係などが合わさって形成される。その人がどのような人であったかを理解し、なじみの生活環境を整えることが大切」「後見人の役割としては本人に最善の環境を提供することであり、人としての尊厳を常に念頭に置き接することが求められている」など学びました。後半は「認知症の人が自宅で生活する条件は?」のテーマでグループディスカッションを行いました。改めて認知症を学び、認知症の人が最後まで社会的に孤立することなく「人として」存在し続けるために支えになることを再認識いたしました。(於:千代田区和泉橋区民会館)
■第9回ひろばの輪 (2017年9月17日)
“わかりやすく成年後見を説明するための一つの手法『KP法』を学ぶ”
成年後見制度を分かりやすく伝える手法として、『KP法』を参加者と学びました。『KP法』とは紙芝居プレゼンテーションの略です。「わかりやすい成年後見制度」のプレゼンテーションを体験しました。(於:飯田橋ボランティアセンター)
■第8回ひろばの輪 (2017年5月13日)
“「成年後見制度利用促進基本計画」について、みなさまと一緒に学び、語り合おう!”
「成年後見制度利用促進計画のポイント」として、①利用者がメリットを実感できる制度運用の改善、②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり ③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和を上げ、特に、「家庭裁判所との連携」を考慮した「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり(中核機関)」について話し合われました。参加者から今後の活動として、「中核機関は重要な役割を果たすことになる。市町村の動きをフォローすることが重要」「行政へ利用促進法利用計画の策定を提言する」「市民目線の研修や話し合いを重ねることが大切」などの意見がありました。(於:渋谷区立勤労福祉会館)
■第7回ひろばの輪 (2017年2月12日)
“伝わる話し方を学び、仲間の発表を聞いてみよう”

第1部では、一般社団法人東京話し方教室 代表久保幸子氏をお招きし、『伝わる話し方教室』と題して講演いただきました。第2部は『仲間の発表』と題して修了生5名の方がそれぞれのテーマで発表されました。
1.人生終盤(第3の人生)への備え(淑徳大学看護栄養学部看護学科 老年看護学助教 岡本 あゆみ氏)
2.「NPO法人 成年後見なのはな」活動報告(10年間の歩み)(認定NPO法人 成年後見なのはな 代表 土井 雅生氏)
3.障害者就業と女性の活躍促進に向けた課題(市民後見促進研究会BON・ART 理事 東 弘子氏)
4.障害者の就業と市民後見の役割 制度のはざま(市民後見促進研究会BON・ART 事務局長 有路 美紀夫氏)
5.遺言の付言について(税理士法人 昴星 代表社員 岩田 克夫氏)
(於:日比谷コンベンショウウセンターホール)
■第6回ひろばの輪 (2016年12月18日)
“聞いてみよう。現役区民後見人から日々の活動について”
墨田区市民後見人として活躍されております清水勇行氏に講演をお願いしました。墨田区と墨田区社会福祉協議会が共催して実施された市民後見人養成講座の内容と、市民後見人になるまでの工程のお話しを傾聴し、後半では、実務として活動されている後見について、事例を紹介いただきながら、市民後見人としての課題と展望をお話いただきました。(於:飯田橋ボランティアセンター)
■第5回ひろばの輪 (2016年9月19日)
“伝言ノートを書くきっかけは?”
介護サポート情報館『たんぽけっと』代表である松本紀子氏(市民後見人養成講座2期生)から伝言ノートについて講演いただきました。松本氏は看護相談をしておりますのでその体験談も拝聴しました。(於:文京シビックセンター)

■第4回ひろばの輪 (2016年7月23日)
“終活から見た後見の役割”
終活コンサルタントである関谷利治氏を講師に招き、在宅介護の体験談を聴き、成年後見の関わりについて考えました。(於:渋谷区立勤労福祉会館)

■第3回ひろばの輪 (2016年5月14日)
“みんなで語ろう。市民後見の役割”
『大阪成年後見の現状』を視聴し、グループに分かれて成年後見の現状について情報交換を行いました。ディスカッションするグループ別テーマは、①市民後見人が期待されていることは(専門職との違い) ②市民後見を広げるためにはどんな活動が必要か ③市民後見制度の問題点は?変更したい点は? ④市民後見を受任するためには としました。(於:飯田橋ボランティアセンター)
■第2回ひろばの輪 (2016年3月12日)
“なぜ広がらない成年後見”
市民後見人について、地域の現状を3グループに分かれ討議しました。問題点として、①活動を進めていく上での費用面 ②つながりや掘り起しの必要性 ③老後の安心設計で後見の周知が必要などが挙げられました。(於:高円寺北区民集会所)
■第1回ひろばの輪 (2015年12月5日)
“認知症高齢者鉄道事故について”
2016年3月に最高裁による判決が下される予定となっている「認知高齢者の鉄道事故」について、JRと加害者家族それぞれの立場に立って、問題点を話し合い検証いたしました。(於:高円寺北区民集会所)